化学物質とアレルギー反応
胎児期や乳児期早期には、脂溶性の化学物質(ダイオキシンやDDTなど)の影響によって、臓器の形成やざまざまな臓器の機能的な発達が異常を起こします。さらには、臓器が形成され機能的な発達が一定終わった後も、化学物質は動物の身体にさまざまな影響を与えます。とくに、哺乳動物では、高度で精密な免疫機能であるアレルギー反応を発達させているため、化学物質によってアレルギー反応がかく乱される可能性があります。また、胎児期に化学物質の影響を受けた個体では、生後も化学物質の影響を受けると、異常な状態を発生させやすい可能性が考えられます。
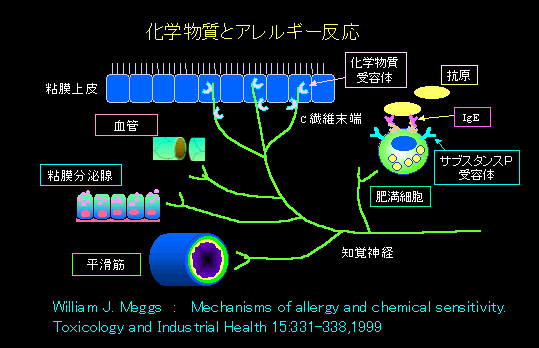
皮膚や粘膜上皮、血管、粘液分泌組織、気管・気管支または腸管等の平滑筋などには知覚神経が張りめぐりネットワークを作っており、各臓器の状態は神経を介して常に中枢神経に送られています。知覚神経であるC繊維の末端には化学物質に結合することができる受容体があるのではないかと考えられていますが(文献1)、まだ確定はされていません。アレルギー反応を起こさせる化学伝達物質(ヒスタミンなど)を蓄えた肥満細胞の細胞表面には、神経細胞から放出される化学伝達物質である神経ペプチド(サブスタンスPなど)を受け取る受容体があることがわかっています(文献2)。つまり、神経が発した情報を肥満細胞は受け取ることができます。
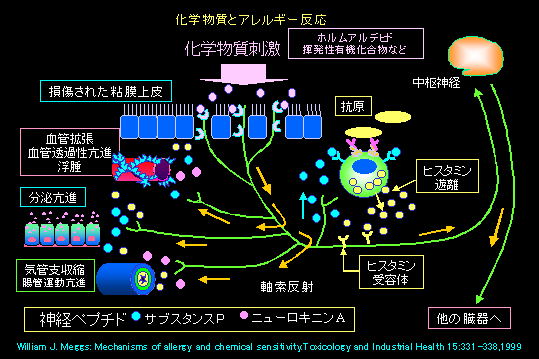
粘膜上皮がなんらかの原因(アレルギー反応や、感染症、ホルムアルデヒドや揮発性有機化合物などの多量の化学物質の暴露など)によって損傷を受けると、知覚神経の末端が露出されます。何らかの環境汚染化学物質が存在すると、その化学物質は神経にある化学物質受容体に結合し、神経の興奮を起こさせます。その興奮は、神経繊維を伝播し、一部は軸索反射という反応によってその臓器の血管、粘液分泌細胞、平滑筋などに興奮を伝え、むくみ、発赤(皮膚や粘膜が赤くなること)・紅潮、粘液の分泌増加(よだれ、鼻水、痰、下痢など)、平滑筋の収縮(喘息発作、胸痛、腹痛など)を起こさせます。また、神経細胞から分泌されたサブスタンスPなどの神経ペプチドは肥満細胞表面の受容体に結合し、ヒスタミンのなどの化学伝達物質の放出を助長させます。ヒスタミンは各臓器の反応を激しくさせると同時に、神経細胞表面に存在するヒスタミン受容体に結合しさらに神経の興奮を激しくさせます。神経の興奮は中枢神経に伝えられ、そこから体内の他の臓器に興奮を伝え、全身の症状が起こります。
化学物質は、各臓器の働きを異常に刺激して症状・病気を引き起こし、かつ、すでにその人が持っていたアレルギー反応を激しくさせていると考えられます。
とくに有機リン系殺虫剤は神経の興奮を増強して調節ができない状態に導き、過剰なアレルギー反応、過剰な神経反応、過剰な化学物質に対する反応を起こすと考えられます。
![]()
![]()